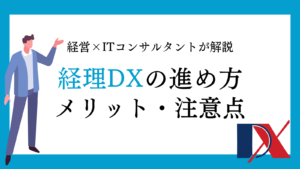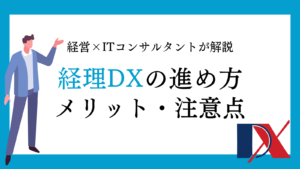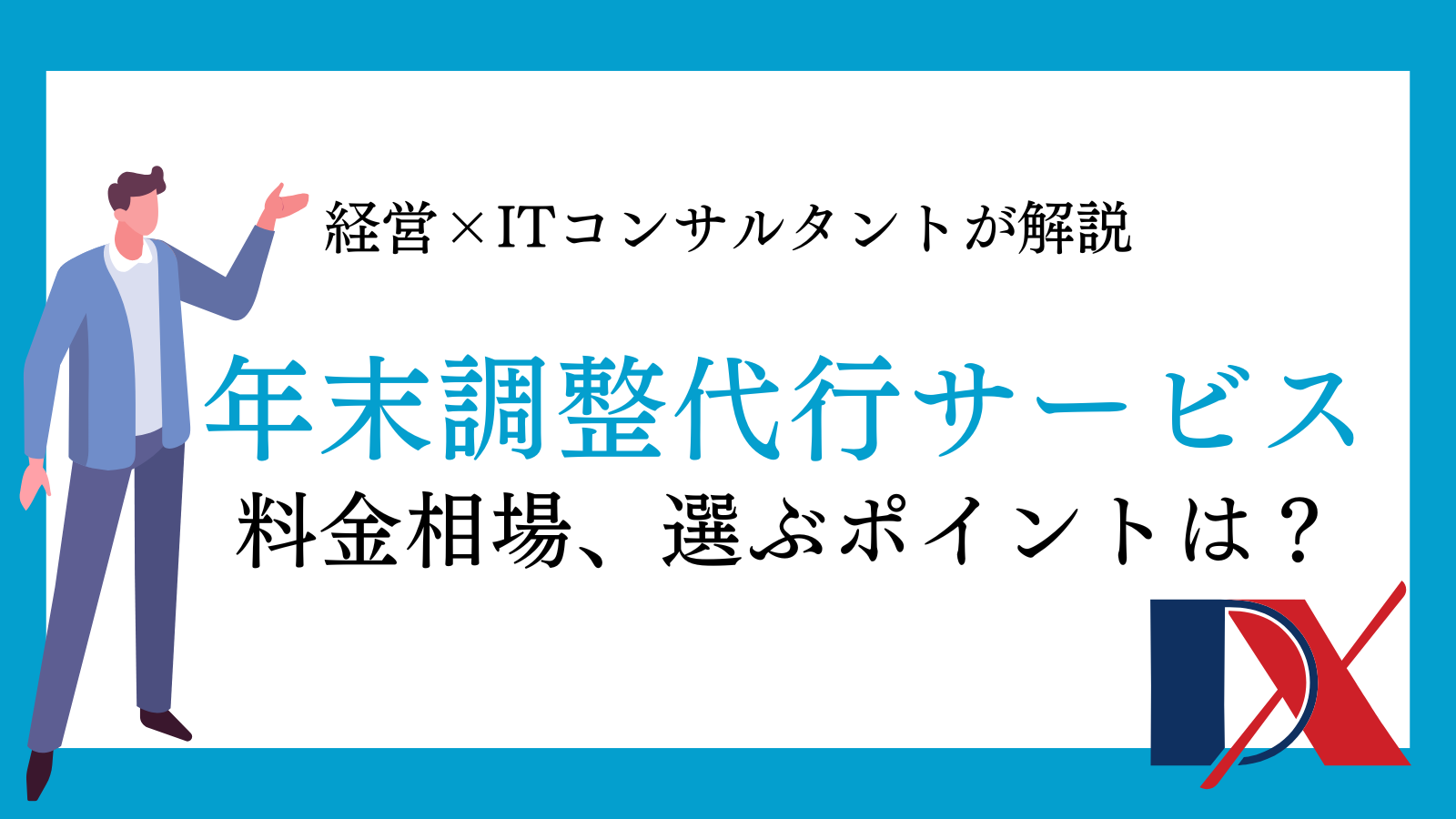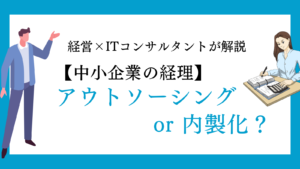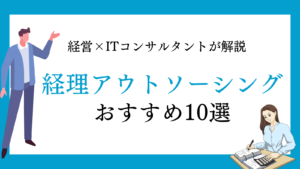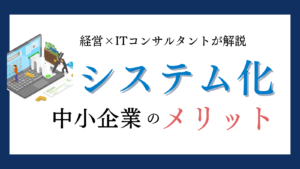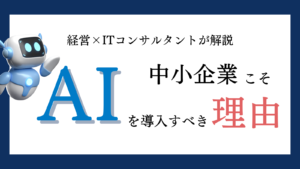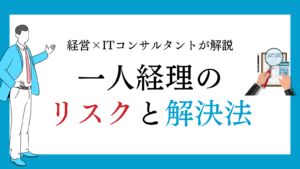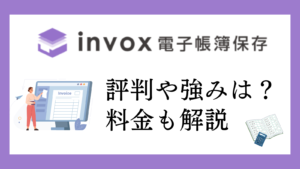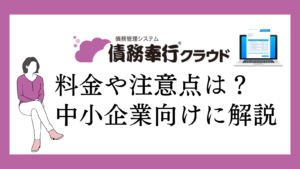毎年、年末になると必ず行わなければならない「年末調整」。1年間に働いた従業員が納める所得税を最終的に調整する手続きですが、中小企業にとっては大きな負担ですよね。
特に人事や経理の担当者が少ない会社では、書類の確認や計算が集中して残業が増えたり、ミスを心配したりすることも多いのではないでしょうか。
そこで注目されているのが「年末調整代行サービス」です。専門家や専門チームにアウトソーシングすることで、手間と時間をぐっと減らし、社内でのミスを防ぐことができます。
この記事では、年末調整代行サービスの概要や料金相場、選ぶ際のポイントなどを分かりやすく解説します。
 ITデザイナー
ITデザイナー自社の状況に合ったサービスを見つけ、年末調整の負担を軽くしていきましょう!
年末調整代行サービス(アウトソーシング)とは


年末調整代行サービスは、会社が行う年末調整の作業を、外部の専門会社に任せる方法です。
毎年末に行う年末調整は、従業員の所得税を正しく計算し直すために必要ですが、提出書類が多かったりチェックが複雑だったりと、手間がかかることが多いですよね。この作業をアウトソーシング(外部に委託)すると、社内の負担を大きく減らすことができます。
年末調整代行サービスで依頼できること
年末調整代行サービスでは、以下のような業務をお任せすることができます。
書類の回収・チェック
従業員が提出する控除証明書などを、代行サービスが回収して確認します。提出漏れや記入ミスがあれば、すぐに連絡して修正してもらいます。
控除額や税額の計算
社内で行うとミスが起きやすい計算を、代行サービスが行います。複雑な税金ルールにも対応できるため、自社の担当者が最新の法改正を追う必要が減ります。
源泉徴収票の作成・配布
年末調整後に作成する源泉徴収票の発行や従業員への配布方法なども代行サービス側でサポートしてくれるので、事務作業の負担が大幅に下がります。



このような業務を代行してもらうことで、中小企業の経営者や担当者が年末調整の細かい作業に時間を取られずに済みます。
社労士や税理士への依頼との違い
社労士や税理士は、労務管理や税務全般の専門知識を持っています。幅広く相談できる一方、すべてをまとめて依頼すると費用が高くなりやすい面があります。
一方、年末調整代行サービスは「年末調整に特化した支援」が中心です。書類の集計やデータ入力、源泉徴収票の作成など、手間がかかる事務作業をまとめて任せられるので、「年末調整だけプロにお任せしたい」という企業に向いています。
年末調整代行サービスの導入が増えている背景
近年、年末調整代行サービスを利用する企業は増加の一途をたどっています。その理由について、以下の3つが考えられます。
人手不足
中小企業では、総務・経理担当者を少数精鋭で行っていることが多いでしょう。年末調整シーズンにはほかの業務も集中するため、残業が多くなりやすくミスが起こりがちです。そこで、アウトソーシングを利用して人手不足をカバーする企業が増えています。
Web対応のサービスが増えている
最近はWebを使って従業員が必要な情報を入力できる代行サービスが増えており、紙書類より手間がかかりにくいのが大きなメリットです。リモートワークでも提出しやすいので、多様な働き方に対応できます。
複雑化する税制への対応
毎年のように税金や控除に関するルールが変わるため、労務にかかわる社員は常に勉強が必要です。しかし、まるっとアウトソーシングしてしまえば最新のルールに沿った処理をしてもらえるので、社員が法改正に対応する工数を減らせます。



アウトソーシングをうまく活用すれば、社内リソースを大幅に節約できますよ。
年末調整代行サービスを利用するメリット


特に中小企業では、限られた人員で年末調整に対応しなければならず、毎年この時期はバタバタしてしまうという声も少なくありません。
そこで、年末調整の業務を専門の代行サービスに任せることで、作業時間を減らし、ミスを防ぎながらスムーズに進めることができます。
ここでは、代行サービスを利用することで得られる具体的なメリットを紹介します。
業務負担を減らし、効率よく進められる
年末調整は、従業員からの書類回収や内容確認、控除額の計算など、細かい作業が多いため、担当者の負担が増えがちです。特に人員が少ない会社では、この時期に仕事が集中して残業が増えることも珍しくありません。
代行サービスを利用すれば、面倒な事務作業を専門会社に任せることができるため、社内の業務負担を大幅に軽減。
専門家に任せられる安心感
年末調整では、税制改正の影響を受けることもあり、毎年ルールが変わる可能性があります。そのため、社内の担当者がすべてを把握しようとすると、調べる時間が必要になったり、計算ミスが発生したりするリスクがあります。
代行サービスを利用すれば、最新の税制に対応した専門家が作業を行うため、ミスのリスクを減らしながら、スムーズに年末調整を進めることができます。
従業員からの問い合わせ対応・紙作業の負担が減る
年末調整の時期になると、「どの書類を提出すればいいのか」「この記入方法で合っているか」といった質問が増え、担当者の時間が取られてしまうことがよくあります。特に社員数が多い会社では、ひとつひとつ対応するだけでも負担が大きくなります。
代行サービスによっては、従業員からの問い合わせ対応を代行してくれるプランもあります。これを利用すれば、社内での対応時間を減らしながら、スムーズに進めることができます。
従業員もスムーズに提出できる
最近では、年末調整の申告をWeb上で完結できるサービスも増えてきました。従業員がスマートフォンやパソコンから情報を入力し、そのまま送信できるため、書類を手書きする手間や、紙を配る・回収する作業が不要になります。
特にリモートワークが増えている企業では、従業員が出社しなくても年末調整を完了できるため、提出の遅れや書類の紛失を防ぐことができます。
年末調整代行サービスの具体的な業務内容とは
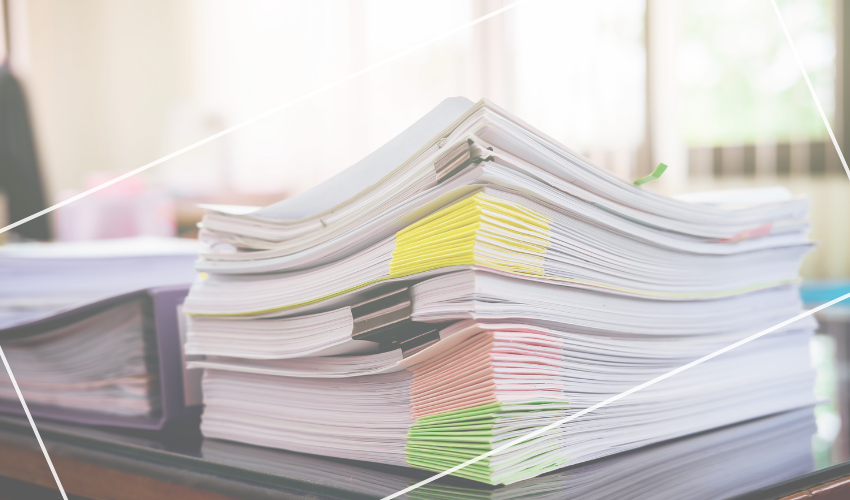
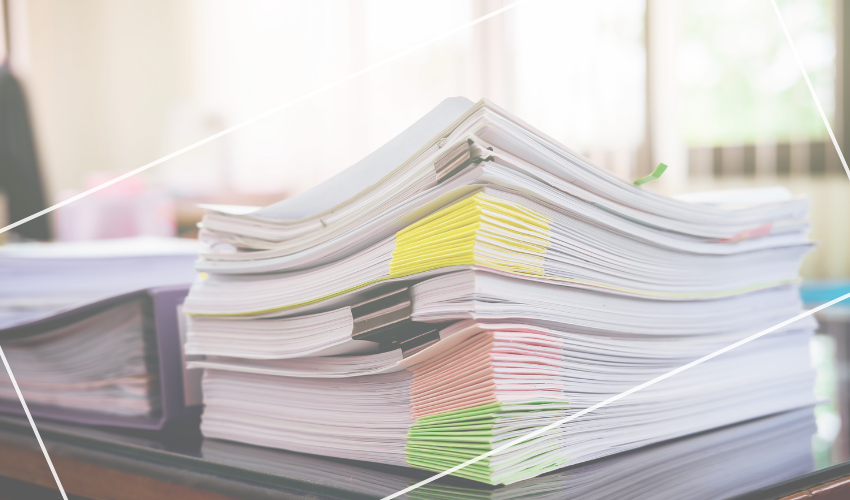
年末調整を代行してくれるサービスでは、企業に代わって面倒な年末調整の作業をまとめて引き受けてくれます。ここでは、その具体的な業務内容を、以下4つの観点から説明します。
必要書類の収集・確認(紙/Web)
年末調整をスムーズに進めるためには、まず従業員から必要な書類を集める作業が必要です。しかし、従業員の人数が多いと、提出の催促や内容のチェックに時間がかかることがよくあります。
年末調整代行サービスを利用すれば、以下のような書類の回収から確認までを一括して任せることができます。
| 扶養控除等申告書 | 扶養している家族がいる場合に提出 |
|---|---|
| 保険料控除申告書 | 生命保険や地震保険などの控除を受けるための書類 |
| 控除証明書 | 保険会社などから送られてくる証明書類 |
提出期限が近づいても書類を出していない人には、代行業者からリマインド(催促)を行うため、担当者が個別に連絡する手間が省けます。また、提出された書類に不備がないかを確認し、記入漏れや間違いがあれば、代行業者から従業員へ修正依頼を出してもらうことも可能です。
紙の書類の場合
代行業者がまとめて回収し、内容をデータ化したうえで、必要な処理を行います。書類の整理やファイリング、必要に応じた返送も対応してくれるため、経理担当者が大量の紙を管理する負担を軽減できます。
オンライン対応の場合
従業員がスマートフォンやパソコンから直接情報を入力できる仕組みを用意してくれます。特にリモートワークが増えている企業では、書類のやり取りをオンライン化できることが大きなメリットとなるでしょう。
源泉徴収票の作成
年末調整が終わった後、企業は従業員に「源泉徴収票」を発行する必要があります。源泉徴収票の作成は手間がかかるうえ、計算ミスが許されないため、担当者にとっては大きな負担です。
年末調整代行サービスを利用すれば、年末調整の結果をもとに、源泉徴収票の作成までサポートしてもらえます。
給与支払報告書の作成
「給与支払報告書」は従業員が住んでいる自治体に提出するもので、翌年の住民税の計算に使われる書類です。この業務も企業側で行うと手間がかかるため、代行サービスを利用すれば、給与支払報告書の作成から提出までをまとめて任せることができます。
申告内容のチェック・問い合わせ対応
年末調整では、従業員が提出する書類に記入ミスがないか、必要な証明書がそろっているかを確認する必要があります。
「どの書類を出せばいいの?」
「書き方が分からない」
年末の時期にはこのような問い合わせ対応に追われる毎日で、担当者の業務が圧迫されてしまいます。
そこで、年末調整代行サービスを利用すれば、申告書類の確認から修正依頼、問い合わせ対応までまとめて依頼することができます。具体的なサポート内容は以下のとおりです。
- 書類の記入ミスや不備をチェック
- 不備があった場合の修正依頼や提出リマインド
- 従業員からの問い合わせ対応
代行サービスを活用すれば、プロの目で正確にチェックしてもらえるため、ミスを防ぎながらスムーズに年末調整を進められるのが大きなメリットです。
最新の税制改正への対応
年末調整代行サービスを利用すれば、税制改正への対応がスムーズになります。最新の法律に基づいて手続きを進めてもらえるため、「ルールが変わっていたことに気づかず、処理を間違えてしまった」といったリスクを避けることができます。
たとえば最近だと、以下のような改正がありました。
年末調整代行サービスを利用すれば、最新の税制を踏まえた適切な対応をしてくれるため、企業側の負担が減ります。頻繁に行われる税制改正に振り回されることなく、本業に集中できる環境を整えるためにも、代行サービスを活用するのは賢い選択といえるでしょう。
年末調整代行サービスの選び方


年末調整代行サービスを選ぶ際は、まずどの業務まで対応してくれるのか、料金はどのくらいかを確認することが大切です。その上で、どんな目的で導入するのかを明確にすると、より適したサービスを選びやすくなります。
チェックすべきポイントを、詳しく解説します。
サービス範囲・料金体系を確認する
サービスによっては、必要な部分だけを任せる「部分委託」や、すべて丸投げできる「フルサポート」もあります。自社の業務負担をどれだけ軽減したいかを考えながら、適したプランを選びましょう。
料金体系は、従業員数による課金が一般的で、一人あたり1,200円〜2,500円前後が相場とされています。
目的別に注目すべきポイント
企業によって、代行サービスを導入する目的は異なるはず。ここでは、以下の4つの目的に分けて、代行サービスを選ぶ際に確認すべきポイントを解説します。
作業負担やミスを減らしたい
- 書類の自動チェック機能があるか(入力ミスや不備を防ぐシステム)
- スマホ・PCで申請可能か(紙の管理を減らし、従業員の負担も軽減)
- 口コミで業務負担軽減の実績があるか(導入後にどれくらい楽になったか)
⇒作業負担やミスを減らしたいときは、書類の回収・確認から源泉徴収票の作成まで一括で任せられるサービスを選びましょう。
既存の業務フローを変えたくない
- 現在の給与・会計システムと連携できるか
- 部分委託に対応しているか(たとえば、計算だけ、問い合わせ対応だけなど)
- 同業他社での導入実績があるか(似た環境でスムーズに運用できるか)
⇒業務のやり方を変えたくない場合は、柔軟にカスタマイズできるサービスかどうかをチェックするのがポイントです。
問い合わせ対応までお願いしたい
- 専用の問い合わせ窓口があるか(電話・メール・チャット対応の有無)
- 対応範囲はどこまでか(一般的な質問だけか、個別ケースにも対応するか)
- 口コミでサポートの質を確認(「対応が遅い」などの評判がないか)
⇒ひと口に「問い合わせ対応あり」といっても範囲に幅があるので、そのあたりをよく確認しておきましょう。
業務プロセスを大幅に改善したい(DX化など)
- Web申請・電子化に対応しているか
- 給与・会計ソフトとのデータ連携がスムーズか
- 導入後の改善実績があるか(「処理時間が○%短縮」などの具体的な効果)
⇒業務のデジタル化を進めたい場合は、クラウド対応の代行サービスを選ぶと、年末調整だけでなく他の経理業務を効率化する足掛かりになります。
年末調整代行サービスの料金相場と費用対効果


年末調整代行サービスを検討する際、費用がどれくらいかかるのか気になる方も多いでしょう。ここでは、一般的な料金モデルと費用対効果の考え方をシンプルに解説します。
代行サービスの一般的な料金モデル
年末調整代行サービスの料金は、「基本料金+従業員数ごとの料金」という形が一般的です。
- 基本料金(相場):5,000円〜20,000円
- 従業員ごとの料金(相場):1,000円〜3,000円/人
例えば、従業員10名の企業なら、総額15,000円〜50,000円程度が目安です。サービス内容や企業の規模によって変動するため、事前に見積もりを取ることをおすすめします。
代行サービスのコストメリット
年末調整を社内で対応する場合には、意外と見落とされがちなコストが発生します。
- 担当者の人件費・残業代
- ミスによる再処理コスト
- 印刷・郵送コスト
これらのコストを踏まえると、代行サービスを利用したほうが安く済むケースも多いです。特に、従業員数が増えるほど社内対応の負担も増大するため、一定の規模を超えたら外部委託を検討するのが合理的でしょう。
最適なサービスを選ぶための試算方法
代行サービスの導入を判断する際は、自社の工数と費用を試算し、トータルで考えてみると良いでしょう。
- 社内対応:担当者1人が3日間かけて処理+残業(人件費5万円+残業代1万円)
- 代行サービス:約50,000円〜80,000円(相場)
この場合、社内対応と外注費用はほぼ同額ですが、担当者が他の業務に集中できるメリットを考えると、アウトソーシングの価値は十分にあります。
導入を検討する際は、「費用だけでなく、社内業務の負担削減やミス防止の効果も含めて判断する」のがポイントです。
年末調整代行サービスを導入する際の注意点


年末調整代行サービスをスムーズに活用するためには、事前に押さえておくべきポイントがあります。ここでは、特に重要な3つの注意点を解説します。
業務範囲と責任区分を明確にする
年末調整の業務には、代行サービスが対応できる範囲と税理士でなければ対応できない業務があります。
- 申告書の回収・確認
- 控除額の計算・データ作成
- 従業員からの問い合わせ対応
- 税務署への申告
- 税務相談や指導
このように、「どの作業を誰が担当するのか」を明確にし、契約時に責任区分を確認することが大切です。
コミュニケーションと情報共有のポイント
年末調整は期限厳守の業務です。代行サービスとスムーズに進めるため、提出期限や対応フローを事前に確認しておきましょう。
| 提出期限の管理 | ・申告書の回収・提出の締め切りを明確にする ・期限を過ぎた場合の対応方法を決めておく |
|---|---|
| 書類不備があった場合 | ・誰が従業員に修正を依頼するのか事前に決める ・不備の対応フローを共有しておく |
これらを決めておけば、ミスや遅延を防ぎやすくなります。
解約や変更時のリスク管理
年末調整の直前に代行業者を変更するのはリスクが高いため、余裕をもった計画が必要です。
- 直前での乗り換えは避け、早めに業者を決定する
- データの引き継ぎ方法を確認し、必要な書類は社内でも保管する
新しい業者へスムーズに切り替えるため、データの移管と引き継ぎを適切に行うことも忘れずに。
年末調整代行サービスに関するよくある質問(Q&A)


年末調整代行サービスを検討する際、多くの経営者が気になるポイントをまとめました。
まとめ:年末調整代行サービスを賢く活用しよう
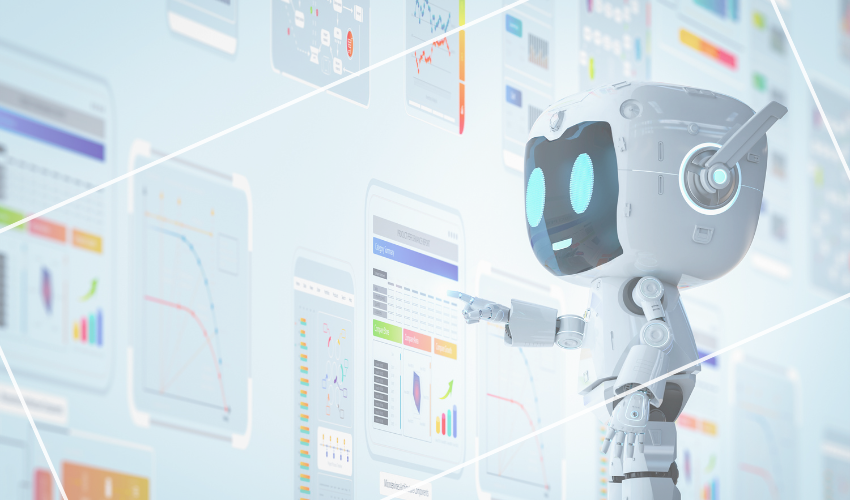
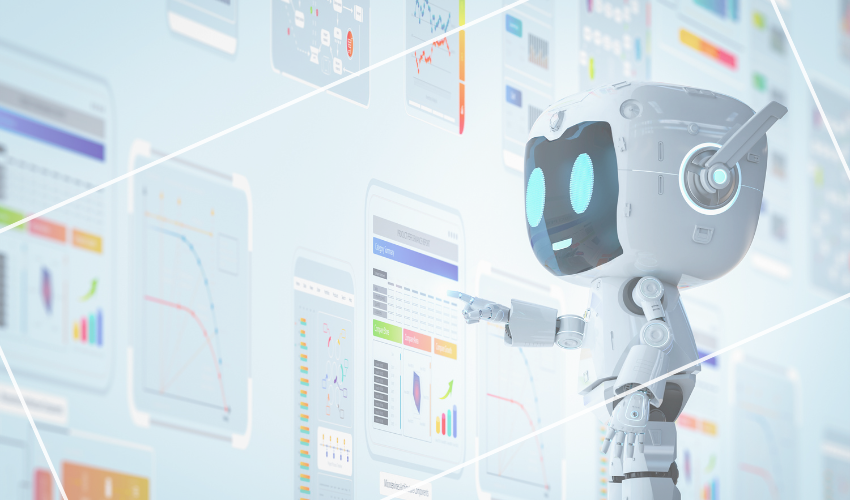
年末調整代行サービスを使うと、作業の負担が減り、ミスも防ぎやすくなります。導入するときは、どこまで対応してもらえるか、追加料金がかかるケースがあるかを事前に確認しておくことが大切です。
会社の規模や今の業務の流れに合ったサービスを選べば、手間が減り、スムーズに進められます。



早めに準備を進めて、年末の忙しさを軽くしましょう。
経理DXを進める方法についてはこちら↓